記事対象年齢:公立小学校に通う小学生
J-SHINEオンライン研修会(第4回)の参加報告と指導用テキスト・英語玩具・英語アニメの紹介

こんにちは。英語講師のAKIKOです。今回、英語講師としてのスキル・知識のアップデートの為に、J-SHINE名誉理事 吉田研作先生によるオンライン研修会 第4回テーマ:『学習指導要領の理解』(J-SHINE®資格者対象)に参加しました。研修会の感想と指導用テキスト等の紹介もしますね♪記事を書いているこの先生はどんな人? → こちらをご覧ください♪
第4回テーマ『学習指導要領の理解』は、どんな研修会だったの?
J-SHINE主催で行われた、J-SHINE®資格者のスキルや知識をアップデートする目的で開催された任意参加のオンライン研修会です。※J-SHINEって何?セミナー第1回内の「J-SHINEって?」の説明をご参照ください。
こちらのオンライン研修会は、2021年9月~12月までの間に、それぞれ異なるテーマで、全5回のオンライン研修会開催予定です。今回は第4回目です。
※第1回のオンライン研修会は、2021年9月2日(木)に既に、終了しています。上記から又はこちらからどのような研修会かご確認いただけます。
※第2回のオンライン研修会も、2021年9月27日(月)に既に、終了しています。前回の研修会についてはこちらから、第2回目「学校文化・教員免許」
※第3回のオンライン研修会も、2021年10月22日(金)に既に、終了しています。前回の研修会についてはこちらから、第3回目「英語力向上」
さて、今回、第4回目「学習指導要領の理解」は下記の通り行われました。
- 日付:2021年11月17日(水)
- 時間:午前10:30~午前11:30
- 場所:オンライン
- 定員:300名
- テーマ:第4回「学習指導要領の理解」
- 講師:J-SHINE名誉理事 吉田研作 先生
講師はどのような方だったの?
J-SHINE名誉理事 吉田研作 先生(上智大学名誉教授)
今回の研修では、ご自身の経歴はお話されなかったので、研修終了後にどんな経歴の先生であるか調べてみました。
京都府生まれ。上智大学外国語学部英語学科卒業。同大学大学院言語学専攻修士課程修了。ミシガン大学大学院博士課程修了。上智大学外国語学部講師、助教授、教授、学部長、特別招聘教授、言語教育研究センター長を歴任。2021年4月より、上智大学名誉教授および公益財団法人日本英語検定協会会長。
「吉田研作」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)
アクセス日時:2021年11月18日 17:15(日本時間)
先生の著書は多くのものがありますが、
『外国人とわかりあう英語 異文化の壁をこえて』(ちくま新書)
『新しい英語教育へのチャレンジ 小学生から英語を教えるために』(くもん出版)
などもありました。
こちらの書籍は記事の最後の方でご紹介しますね。
なぜ研修会に参加したの?
小学生に指導をする機会が多い私。今回の「学習指導要領の理解」の研修会とは、現在親世代(30代~50代)が学生時代に受けた英語教育の内容と何が違うのかということを知りたくて申し込みをさせていただきました。
2.英語学習要領の違いのメリットは何か?
3. 家庭で取り組むべき事は何か(英語学習・英語楽習)?
研修会スタート

参加者の皆さんは、J-SHIN資格者です。※J-SHINEって何?セミナー第1回内の「J-SHINEって?」の説明をご参照ください。
研修会内容
以下の内容でオンライン研修会は行われ、現状を学びました。
(1)日本の英語教育の推移
(2)アクティブ・ラーニング
(3)Can-do評価
(4)質疑応答
※セミナー著作権が関係してきますので、セミナー内容を詳細に記載することはできません。ですので、セミナーを受けて私が感じた事を、自分の経験に上乗せして書き留めたものになります。又、既に一般公表されている内容に関しては簡易化してご紹介したいと思います。尚、吉田先生よりご教授いただいた内容は以下” ”で書かせていただきます。
日本の英語教育の推移
私達、親世代(30代~50代)が学校で英語を習い始めたのは中学生からでしたね。今は、小学3年生から外国語活動の時間で英語に触れ始めます。※詳しくは、第1回「小学校英語の今」をご覧ください。
基本的に、日本では英語は外国語-EFL(English as Foreign Language)として実存しています。どういうことかと言うと、日常で英語を使う場面はあまりなく、英語を話せなくても日常生活には困らない環境であるということですね。
このEFLという環境を踏まえて、
【従来の英語教育】では、コミュニケーションとして英語を使うことに重視するよりも、文献などを読むことにより英語を学び、知識として(文法・語法・発音等の正確さ)学ぶことを最も重要としていた。
と、吉田先生よりご説明を受けました。
確かにその通りですよね。私達親世代は文法をひたすら習い、穴埋め問題を解き、まるで数学の公式を覚えるような感覚で英語のテストを受けていたのではないでしょうか?
ですが、どれだけ文法を勉強すれば話せるようになるのでしょうか?、、、というよりも、話せるようになりませんよね?何が足りなかったのでしょうか?
英語指導法には様々な観点からアプローチする方法が提唱されていますが、、、そうです、私達に足りなかったのは知識を実際に使いこなす為の実践練習が不足していたんですね。
そして、
1989年には学習指導要領が「外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てるとともに、言語や文化に対する関心を深め、国際理解の基礎を培う」となる。
と推移してきたというご説明を受けました。要するに、「英語でコミュニケーションを図ろうとすることが大事だ!!」という考え方が、学校教育でも1989年には重要視されはじめたのですね。
そして、現在の小学校では、
アクティブ・ラーニングを取り入れた帰納的学習に重視した指導要領となっている。
とのことです。↑「アクティブ・ラーニング」は後ほど説明しますが、「帰納的学習」というのは体験を通して生徒自身が気づいて習得する学習方法のことです。
このように、親世代から現代の子供世代に「新しい英語学習指導要領」のバトンが渡され、英語教育が劇的に推移してきたのですね。
アクティブ・ラーニング
アクティブ・ラーニングとは
教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れ
た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、
教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査
学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク
等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。出典:文部科学省「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~(答申)」「用語集」
ということですので、親世代の学生時代の様子とかなり変わりましたね。以前は、「先生が授業内容を講義し、生徒は進行を妨げないように静かに講義を聞いて、その内容をノートに書き留める」という、いわゆる、卓上での勉強がメインではなかったでしょうか。
それが、生徒自身が主体となって、与えられた情報から、使える情報を取り入れ、実際に使って行く。「先生や親や誰かに言われたからやる」という他力本願ではなく、自分で考え・判断し・決断するという主体性が養われますね。体験を通して生徒自身が気づいて習得する「帰納的学習」は、学びの本質ですね。
小学校における外国語活動・外国語授業でも、この「アクティブ・ラーニング」を軸に指導されはじめたわけです。親世代から現代の子供世代に、新しく渡されたバトン「アクティブ・ラーニング」によって英語学習が、、、
✔自分で見て真似て身に付ける
✔自分で調べて身に付ける
等々、「自主的に学べる体制の中で、コミュニケーションの道具として身につける」ように変わってきたのがメリットですね。
Can-do評価
前回、お話したCEFR(セファール:ヨーロッパ言語共通参照枠)で採用している言語習得の評価基準です。詳しくは、第3回目「英語力向上」をご覧ください。
そもそも、英語の評価って難しいですよね。「私、現在形が完璧に分かの。凄いでしょ!」ってことでしょうか?それとも、「私、難しい文章が読めるの。凄いでしょ!」ってことでしょうか?うーん。どちらも良く分からない評価ですよね。
そこで、外国語で何が出来るか(Can-do)という「ものさし」を使って言語習得の評価をするCEFRが言語習得の評価基準となったんです。
評価のものさしは6段階(A1・A2・B1・B2・C1・C2)です。A1・A2は基礎段階の英語使用者・B1・B2は自立した言語使用者・C1・C2は熟達した言語使用者です。
小学生が、今後、目指していくレベルは基礎段階の英語使用者ですね。
例えば、
✔簡単な質問をしたり、簡単な質問の受け答えをしたり
✔簡単な語句や表現を読めたり(又は、いくつかの提示された例文の中から適したものを選び出したり)
✔例文を参考に簡単な語句や表現を書き写したり
という目標が達成するように、学校では自主的に英語で出来ること(Can-do)を増やしていくんですね。
Can-do 評価を通して、お子さんが英語で出来ることを、たくさん褒めてあげましょう!!

でも、待って!! やっぱり、学校だけの英語時間は少なすぎる!! お家でも、英語時間を作って英語に慣れ親しんでほしいです。それは、パパ・ママと一緒に楽しく英語で遊ぶことですね。英語で遊べる玩具を後ほど紹介します。是非、お子さんと英語時間作ってください♪
質疑応答

今回、時間の関係で私の質問にお答えしていただくことが叶わなかったのですが、私がお聞きしたかった質問は、
留学した経験があるのですが、その際、私が学生時代に習ってきた「はっきりと、分かりやすい英語」をネイティブの日常会話として聞く事はありませんでした。これから、英語を習う小学生には「はっきりと、分かりやすい英語」の他に、「ネイティブの日常の音声」の両方を身に付けて欲しいと思います。何かアドバイスをいただけないでしょうか?
という内容だったので、今回は、私が次のように提案させてもらいます。
まず、
② 身につけた後、(または同時に)英語のアニメを見て、①で身につけた音と、アニメで聞く違う音が、「実は同じ音である事」に気づかせる。
では、次の項目で、吉田研作 先生の著書の紹介と一緒に、私が選んだ、「家庭で出来る音声付の玩具とアニメ」をパパ・ママに紹介させていただき、解決策の1つとさせてもらいますね。
書籍・英語玩具・英語アニメ
まず、吉田先生の著書をご紹介!!
まとめ
研修会では、今回紹介させていただいた事に加えて、他にも沢山の内容をご教授いただきました。今後も、指導者としてのスキルや知識をアップデートしていきたいと思います。
第4回テーマ『学習指導要領の理解』では、英語講師が、
①「現在の英語教育がアクティブ・ラーニングに基づく生徒の自主性を育てる事が大切であること」を念頭に置いた指導を行う。
②Cand-do評価に基づく指導を行う。
③Can-do評価に基づいた適正な評価をすることが必須。
と学びました。パパ・ママのご家庭でのご協力も、子供のこれからの英語力に大きく影響を与えると思います。ご家庭でお子さんと英語遊びをする等、是非、皆で一緒に英語教育を盛り上げましょう!!

最後までお読みいただきありがとうございます。
最後に、パパ・ママのブレイクタイム
パパ向けに楽しめそうな情報載せておきますね。
①Amazon 洋書ベストセラー![]()
②Amazon 家電ベストセラー
③Amazon カメラベストセラー




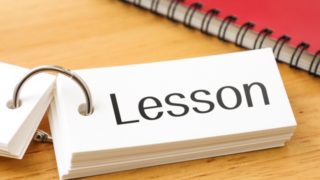







コメント